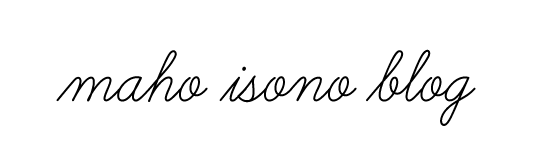風当たりの強い「頑張れ」
この数年「頑張る」への風当たりが強い。「頑張れ」なんて言ってしまったに日は、方々から非難が飛んでくるのでは、というほどだ。
でも、改めて考えてみたい。「頑張る」はそんなにダメなのか。
確かに「頑張る」には問題もある。この言葉には全く具体性がない。「玉ねぎがもう少し透明になるまで炒めよう」と言われれば、これからやることがわかって安心するが、「頑張って炒めて」と言われてもなんのことかさっぱりわからない。
加えて、「頑張る」には際限がない。うまくいかない人に対し、「頑張りが足りない」というのは楽だし、それっぽい感じがする。
でもすでに頑張っている人にこの言葉を重ねても意味がないし、「頑張る」には際限がないので「頑張れ」を使い続け、人を追い込むことだって可能だ。
だから「頑張る」はハラスメントの種となる。
「透明になるまで炒める」と「頑張って炒める」の違い
しかしここで考えてみたい。「玉ねぎがもう少し透明になるまで炒める」と「頑張って炒める」はそもそも位相が違うのではないか。
「透明になるまで炒める」は手順を説明している。他方、「頑張って炒める」は炒める人の身構えを示している。
適当に炒めることと、頑張って炒めることは、出来上がりが全く同じであったとしても異なる。
頑張るというのは、いやでもなんでも、そのことに向き合い続ける、というニュアンスが入っていて、「透明になるまで炒める」にはそれがない。
機械には「透明になるまで炒める」ことはできるが、「頑張って炒める」ことはできないはずだ。
「頑張る」しかない時
世の中には方法で乗り切れることと、そうでないことがある。
おそらく「美味しいカレー」はそのかなりの部分を方法、つまり手順で乗り切れることができる。しかし私たちが人生で出会い、関わらなければならないことには手順がないことも多い。あったとしても、それが正しいかわからないことも多い。
例えば「お金持ちになる」は「幸せになる」ための1つの方法かもしれない。とはいえ、お金持ちでも幸せになれない人はたくさんいるし、お金がなくても幸せな人はたくさんいる。
幸せになるための方法を語る本はたくさんあるが、そこに書いてあることが確実ではないことは、毎年毎年似たような「幸せ本」が出ることからすぐにわかる。
絶対に成功する方法がないのなら私たちにできることは何か。
それが「頑張る」である。
上手くいかなかったとしても、目の前の物事に取り組み続け、その先に自分にとってそれなりにいい方法があり、道が開けるだろうと信じる。それが「頑張る」だと私は思う。
「頑張る」はやり方がはっきりしないときに有効な身構えなのだ
「手放す」と「続ける」を頑張る
2020年に大学を離れる決意をしてから頑張ったことが2つある。それが、「手放すこと」と「続ける」ことだ。
「手放す」ことも「続ける」こともときによっては結構大変だ。手放すこと、あるいは続けることによって状況がより悪くなることもある。それにより嫌な思いをする人が出たり、陰口を言われたりする可能性もある。
加えて「手放し方」と「続け方」に正解はない。
でも「手放すこと」と「続けること」が自分のその先にとって必要だと思えるなら、「手放す」と「続ける」を、その過程でたとえ失敗があったとしても「頑張って」やり続けるしかない。
人は往々にして「頑張るべき」ときに「頑張らず」、「頑張らなくていい」ときに「頑張って」しまうのではないかな。
「頑張る」は最近人気がないけれど、それ自体は人生を歩む上でとても大切な身構えだと私は思う。
参考文献:木村大治『見知らぬものと出会う』