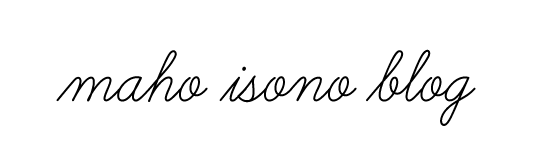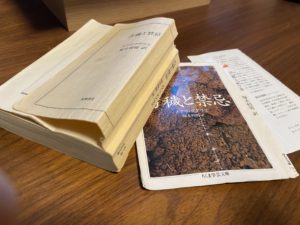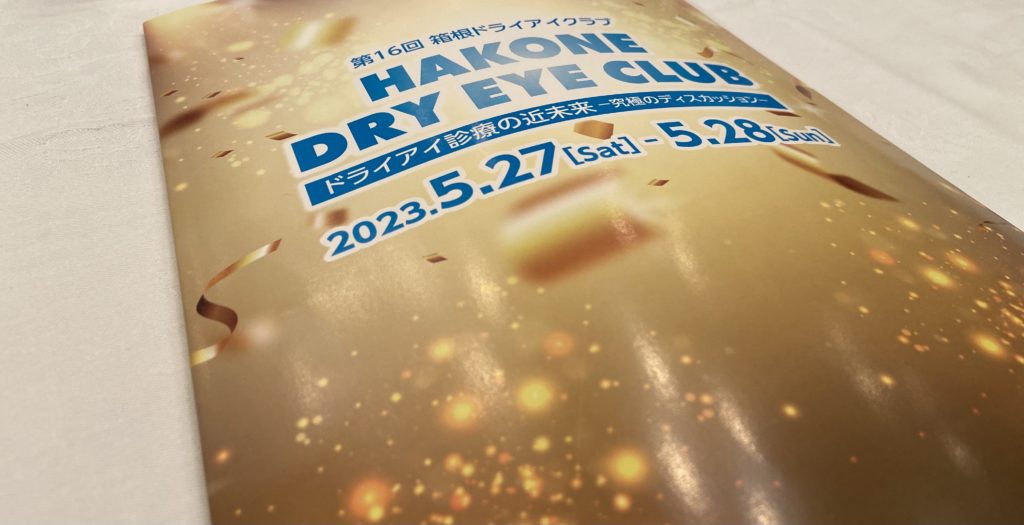
新聞掲載の記事がご縁で、眼科医の横井則彦さん(京都府立医科大学)より、ドライアイ研究会へのお招きを受ける。
ドライアイが眼科の1領域として存在することを全く知らなかったため、お話をもらった時まずそれに驚いた。なんでも日本はドライアイの研究は世界的にもかなり進んでいるのだそうだ。
横井さんからいただいたお題は「痛みとは何か」。
当日は講演時間より少し早めのタイミングで会場入りし、発表を聞いて「ドライアイ」の雰囲気を味わうことに。
予想通り、研究発表は何を言っているかさっぱりわからない。
が、わからないなりにメモをたくさん取る。
涙腺プラグとか、ドライアイは細菌叢が原因となりうるとか、「これは手術の名前?」と思ったら、病気の名前だったりとか。
自分の体に二つある器官の話なのに、お話は文字通り異次元状態。
全くわからなくても、知らないことに触れている、という感覚はワクワクする。
あとドライアイがひどくなると、目を閉じていても痛い場合があるのだという。ドライアイは瞬きをいっぱいすれば治るんじゃないかと思っていた、自分の浅はかさを思い知る。
ドライアイ、深い、広い。
また私の講演の司会をしてくださった同じく眼科医の内野美樹さんは、アイペイン外来というのを開かれているのだそう。
またしても「そんなのがあるのか!」と驚く。
目の痛みで困ってしまう人は意外といらっしゃるのだそう。そういう方たちに、この外来は文字通り救いに違いない。
文化人類学とドライアイ。
一体接合なんてするのかしら、と思っていたけど、想像以上に関連性があり、参加されていた眼科医の皆さんは大変熱心に聞いてくださった。
「医学の観点からは説明しづらかった症例を人類学で理論的に説明できることを知って感銘を受けた」といったありがたいお言葉もいただく。
ディスカッションも盛り上がり、大変学びの多い1日でした。お招き本当にありがとうございます。
ちなみに研究会のお手伝いには参天製薬さんが入っていたのだが、私が持っていた目薬はロート製薬であった。「すみません….」と心の中で謝罪。