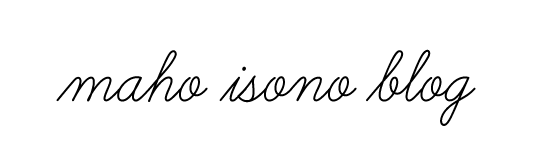本日は、第15回関西サイコオンコロジー研究会にお招きいただき、医療人類学に関する講演をさせていただいた。私は特別講演IIの担当で、Iの担当は、「がん医療における患者-医療者間のコミュニケーションガイドライン 2022」の策定に関わられた、医師の秋月伸哉さん。
冒頭からやらかしてしまった…
がん医療のガイドラインは、医療者だけでなく、患者側からも求められていた。しかし、がん医療のコミュニケーションに関するエビデンスは少なく、策定は大変に難航したそうだ。
が、コミュニケーションをエビデンスでガイドライン化することそのものに、私は違和感を感じてしまった。結果、その違和感をそのまま講演の冒頭で述べてしまうという、変なオープニングを作ってしまうことに…。
今年は、日本サイオンコロジー学会にもお招きいただいたのだが、もう本日でブラックリスト入りかもしれない。
私は、初作の『なぜふつうに食べられないのか-拒食と過食の文化人類学』に始まり、宮野さんとの共著『急に具合が悪くなる』、近刊『他者と生きる-リスク・病い・死をめぐる人類学』で、医学の観点から人間や、人間との関わり方を定式化することへの違和感をずっと述べてきた。だから、コミュニケーションのガイドライン化に違和感を覚えたのは、今考えると既定路線だったとは思う。
人は手引きが欲しいもの
それはさておき、エビデンスがとにかく求められる医学において、患者との望ましいコミュニケーションの在り方を示そうと思えば、エビデンスを探し、それをもとに推奨度を決めていくしかないだろう。
告知のタイミングや余命に関する質問をされ、現場の医療者が悩むこと。医師からひどいことを言われ患者さんが深く傷つくこと。その双方を耳にする。だから、「ガイドラインを!」という流れについては、「そうだろうなあ」と思う。
が、それでもなお、エビデンスに基づくとこういうコミュニケーションは推奨されるとか、されないとかいったガイドラインは、コミュニケーションの大切な部分を削ぎ落としているように見えてしまう。
コミュニケーションは、予測不可能な部分を含み込んだ上で継続されるやりとりであるから、その予測不可能性をエビデンスで狭めていくという手法自体が、コミュニケーションという営みそのものと矛盾するように感じられるからだ。これを突き詰めるとコミュニケーションはタッチパネルみたいなものになるだろう。(もちろん、本日の秋月さんのお話がそこを目指していたわけではないのはよくわかる)
あと患者さんを傷つけないためのコミュニケーションに、エビデンスを示す必要なんてそもそもあるのかしら?とも思う。
とはいえ、「Aという語りかけをすると患者さんの不安が○%上がります。なのでAという語りかけはやめましょう」みたいに示され初めて、「そうか!Aは良くないんだ」となる医療者も一定数いるのだろうか。
コミュニケーションの予測可能性を、文化ではなく医学が担う社会とは?
ただ、コミュニケーションの予測可能性を、これまで文化が担っていたことを踏まえると、それが医学にスライドしただけととることもできる。
どうやったら人を傷つけないか?
どうやったら失礼にならないか?
そういう問いに答えるコミュニケーションの作法は、それぞれの地域が持つ文化の中である程度決められており、それがコミュニケーションを安定させるとともに、共同体の多様性も作り出していた。
この部分を文化ではなく医学が担うと、多様性は減少し、コミュニケーションの安定性が1つのやり方で保証されるような大きな共同体が生まれるだろう。
多様性とか、個性とか言いながらも、このような社会を多くの人が望んでいるのもまた事実だと思うので、「エビデンスに基づくコミュニケーションのガイドライン」はこれからますます増えていくと予想する。